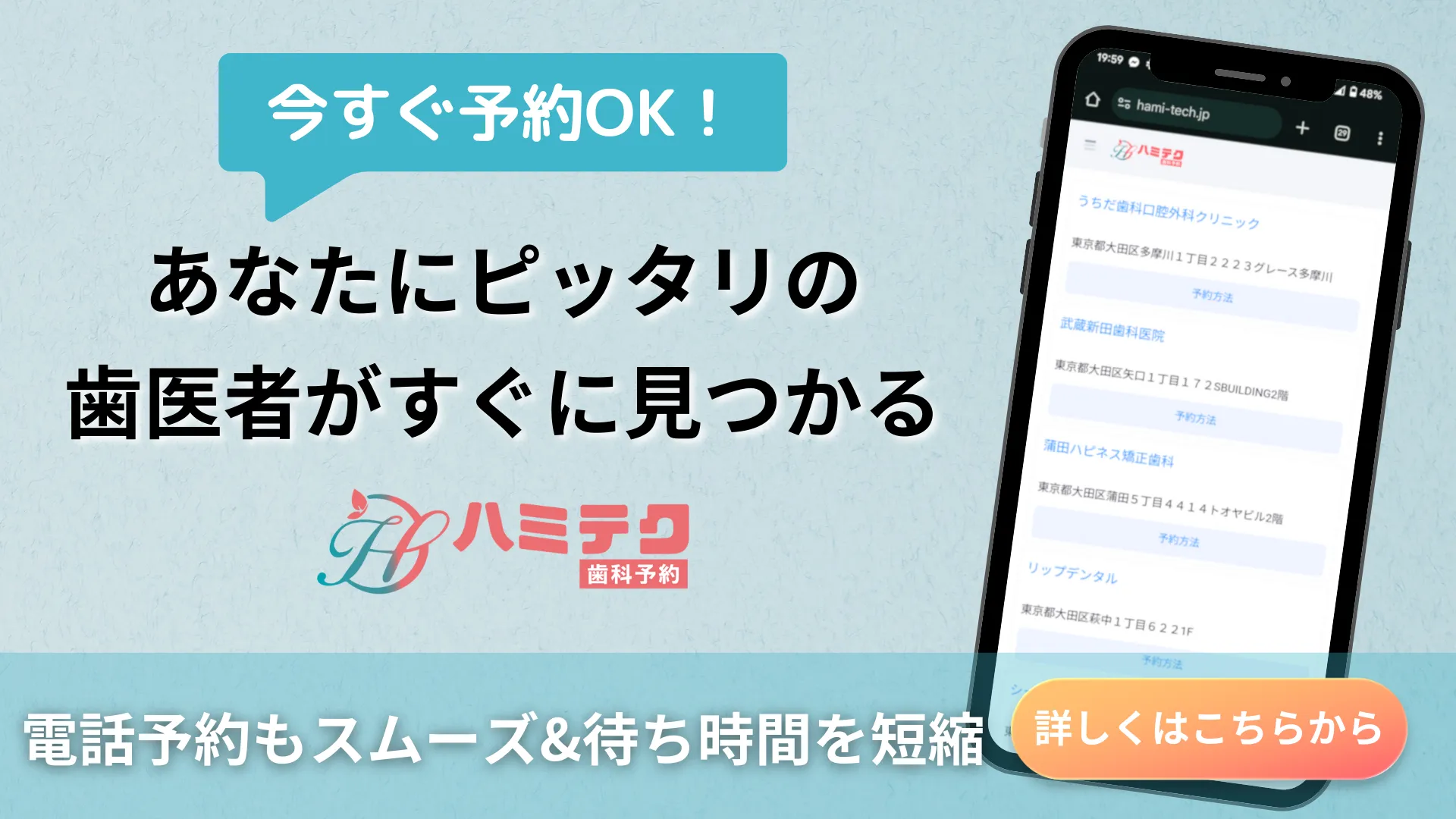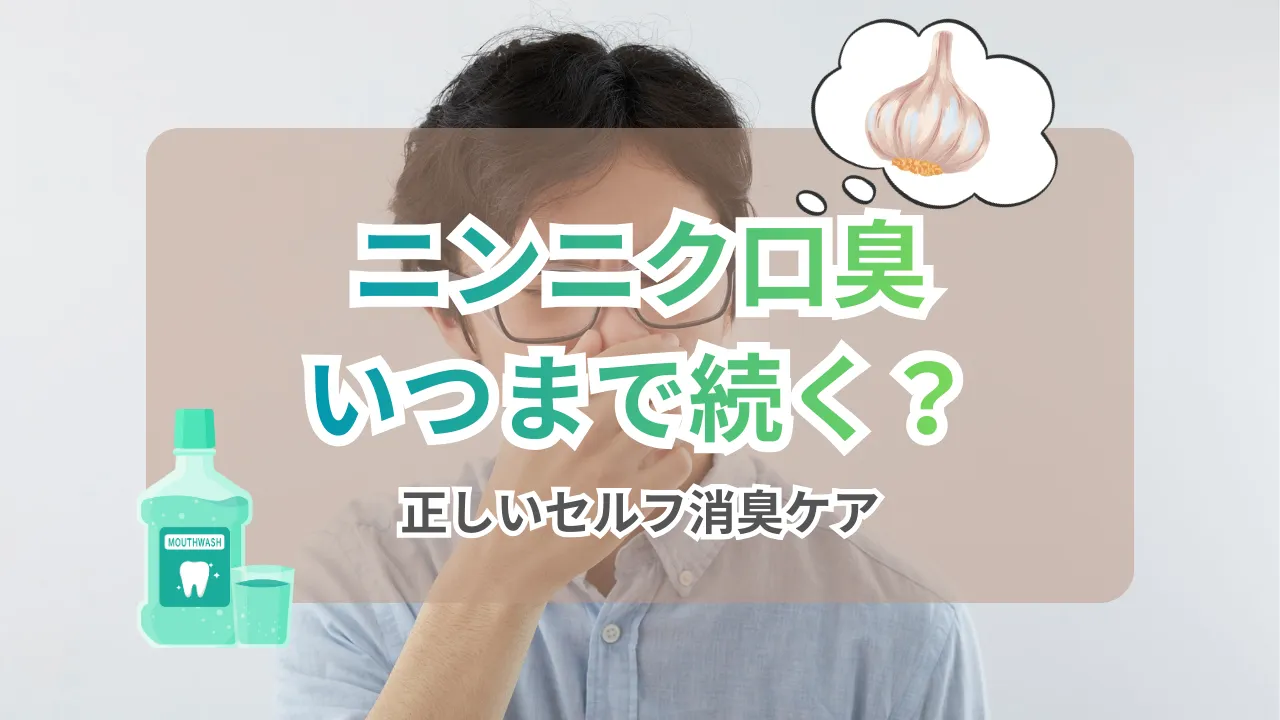歯周病が口臭の原因になる理由と正しい対策
更新日:2025.03.22
歯周病は、私たちの口腔内の健康に大きな影響を与えるだけでなく、口臭の主な原因のひとつとしても知られています。
この記事では、歯周病と口臭の関係について詳しく解説し、なぜ放置すべきではないのか、そしてどのように対策を講じるべきかを紹介します。
目次
歯周病とは
歯周病とは、歯と歯ぐきを支える「歯周組織」(歯肉・歯槽骨・セメント質・歯周靭帯)に、細菌が感染・繁殖し、炎症や破壊を引き起こす慢性的な疾患です。
プラーク(歯垢)に含まれる細菌が、歯の表面に付着して歯石を形成し、炎症を引き起こすことが原因となります。プラークは食べかすや唾液中のタンパク質を栄養源とする細菌の集合体で、これが硬化して歯石になると、通常の歯磨きでは取り除きにくくなります。
歯周病の進行段階
1.歯肉炎(Gingivitis)
歯周病の初期段階であり、歯肉のみに炎症が見られる状態です。歯肉が赤く腫れ、出血しやすくなることがありますが、この段階であれば適切なケアで元の健康な状態に戻すことが可能です。
2.歯周炎(Periodontitis)
歯肉炎が進行すると歯周炎になります。歯と歯ぐきの間に「歯周ポケット」ができ、細菌が奥深くに入り込み、歯槽骨や歯根膜などの歯周組織が破壊されていきます。進行すれば歯がぐらつき、最終的に抜け落ちるリスクもあります。
歯周炎と歯肉炎の詳しい解説はこちらをご覧ください。
歯周病が口臭の原因となる理由
歯周病が進行すると口臭につながるといわれています。ここではその原因を3つご紹介します。
原因1:細菌の繁殖
歯周ポケット内にプラークや歯石がたまると、そこに多くの細菌が繁殖します。これらの細菌は、食べ物のカスや口腔内のたんぱく質を分解し、**揮発性硫黄化合物(VSC)**と呼ばれる臭気成分を生成します。これが口臭の主な原因のひとつです。
代表的な歯周病菌
- ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)
- プレボテラ・インターメディア(Prevotella intermedia)
- タナレラ・フォーサイシア(Tannerella forsythia)
- トレポネーマ・デンティコラ(Treponema denticola)
これらの細菌は、炎症を引き起こすだけでなく、悪臭の元となる物質も作り出すため、口臭の悪化につながります。
原因2:歯肉の炎症
歯肉に炎症が生じると、腫れや出血だけでなく、歯周ポケットの形成が進み、細菌がさらに繁殖しやすくなります。
炎症によって組織が破壊されると、そこに細菌が入り込みやすくなり、分解産物や出血によって不快な臭いが強くなる可能性があります。初期の歯肉炎の段階で対処すれば、進行を食い止めることができます。
原因3:歯の喪失と咀嚼機能の低下
歯周病が進行して歯を失うと、咀嚼が不十分になり、食べかすが口の中に残りやすくなります。これが細菌の栄養源となり、さらに口臭の原因となる可能性があります。
歯周病と口臭を放置するとどうなる?
歯周病を放置してしまうと、口臭の原因となる細菌が増殖し、炎症が慢性化して口臭が日常的に続く状態になります。
また、歯周病によって歯が抜けたり、噛み合わせに支障をきたすと、食事や会話にも影響が出るため、QOL(生活の質)が大きく低下する恐れもあります。
口臭を防ぐためにできること
歯周病の進行を防ぎ、口臭を抑えるためには、以下のようなセルフケアとプロフェッショナルケアの両立が必要です。
- 毎日の丁寧な歯磨き(歯と歯ぐきの境目まで意識)
- デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯の間のプラーク除去
- 定期的な歯科検診と歯のクリーニング(スケーリング)
- 生活習慣(喫煙・食生活)の見直し
セルフケアで使える歯ブラシや電動歯ブラシは以下の記事で紹介しています。
セルフケアで使えるデンタルフロスは以下の記事で紹介しています。
自宅でのケアと歯科定期検診で歯周病を防ぎましょう
歯周病は単なる歯ぐきの病気ではなく、口臭の大きな原因となる慢性的な感染症です。細菌の増殖や炎症の放置は、口臭だけでなく歯の喪失という深刻な問題にもつながります。
日頃のセルフケアと定期的な歯科受診を習慣化することで、歯周病の進行を防ぎ、健康で清潔な口腔環境を保つことができます。
記事を読んでみて心当たりが多かった人もいたのではないでしょうか。口臭や歯周病は歯医者の定期的な受診で改善できるといわれています。
姉妹サイトの「ハミテク歯科予約」では、お近くの歯医者を探すことができます。通いやすい歯医者を見つけて口内の健康を維持しましょう。