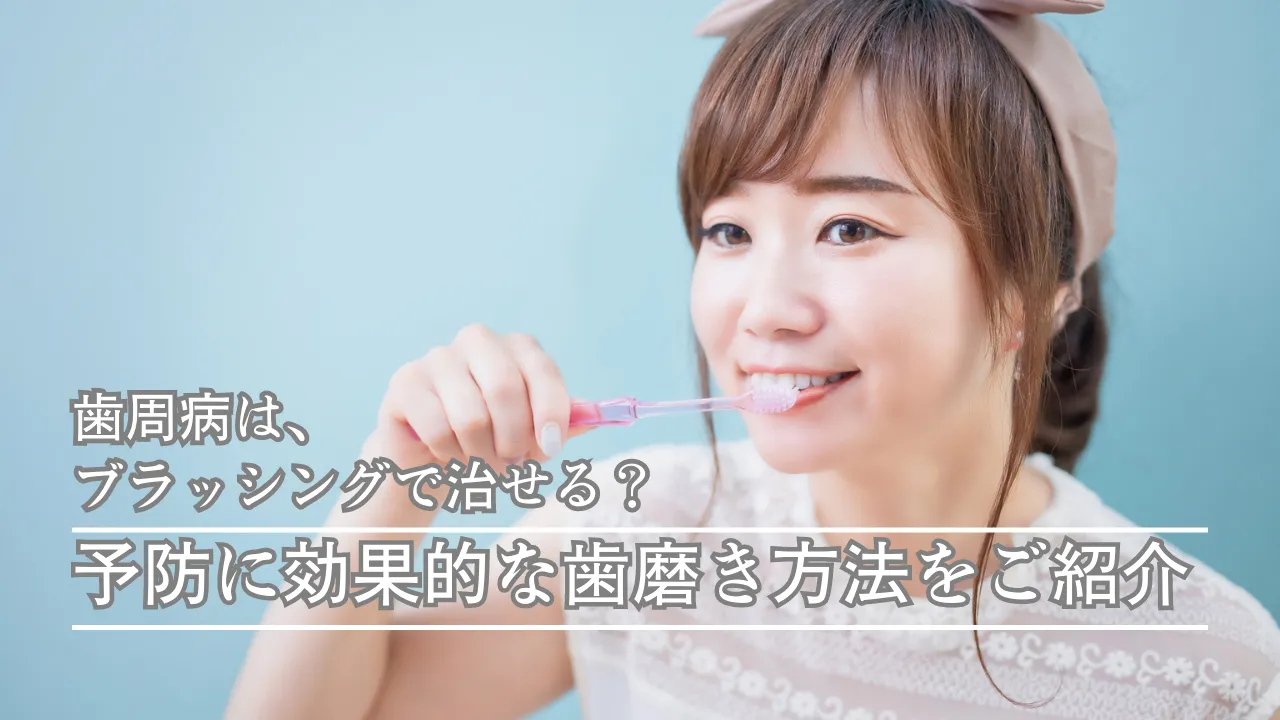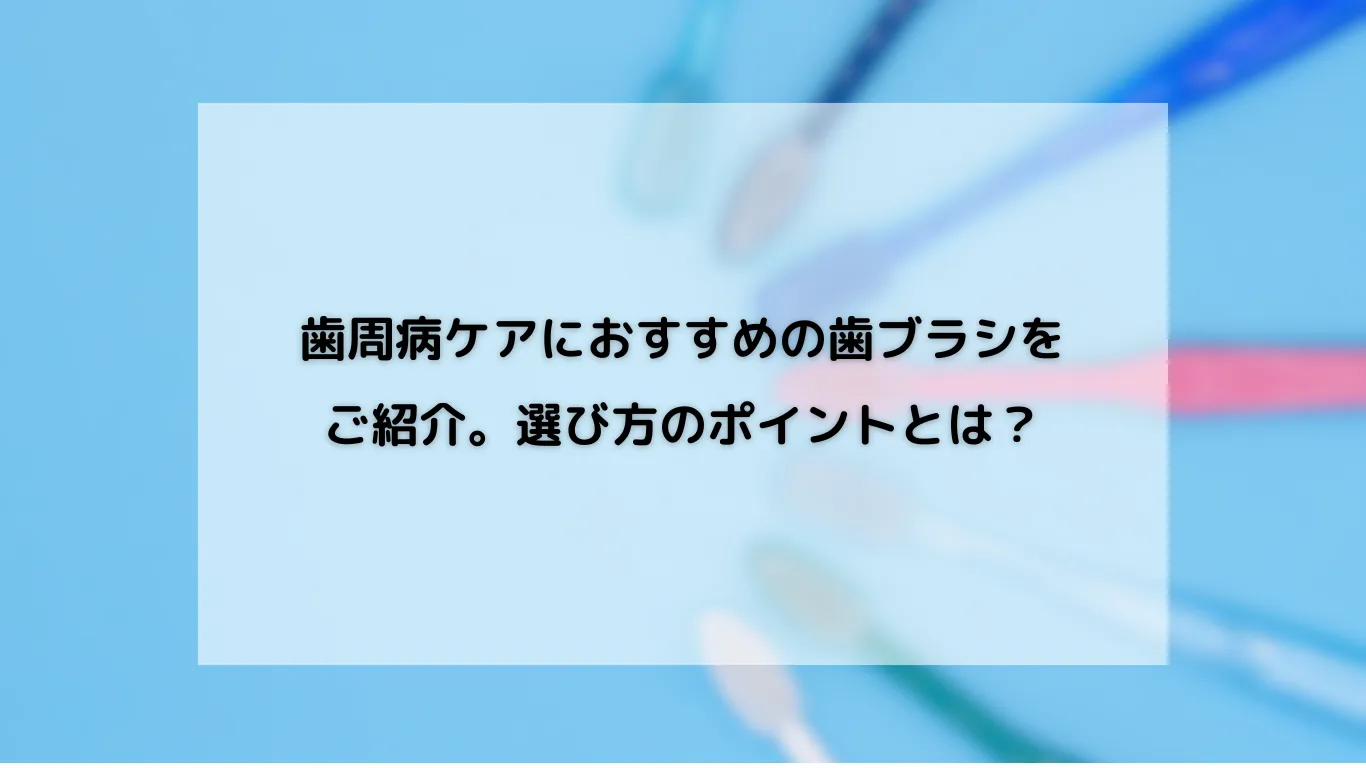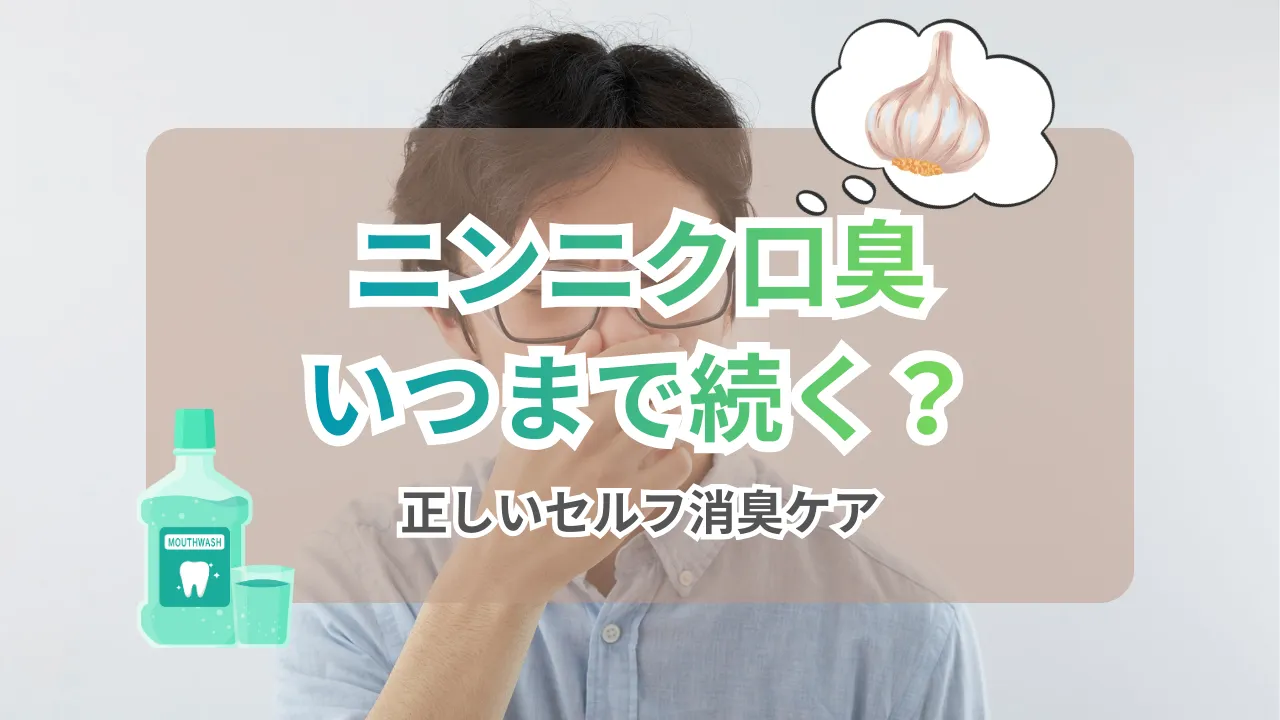歯茎に膿がたまったらどうすべき?応急処置の方法や症状、原因を解説
更新日:2025.11.03
「歯茎が腫れてきたと思ったら、白いできものができた」「歯茎を押すと膿のようなものが出る」「噛んだときにズキッと痛む」といった症状に悩まされていませんか?
歯茎に膿がたまる状態は、見た目の問題だけでなく、激しい痛みを伴う可能性があるため、決して軽視できません。
本記事では、膿がたまる症状や原因、いますぐできる応急処置の方法などを詳しく解説します。
目次
歯茎に膿がたまった時の症状
歯茎に膿がたまると、さまざまな不快な症状を引き起こす可能性があります。ここでは、代表的な症状を解説します。
歯の周りが腫れる
歯茎に膿がたまっているときのわかりやすい症状の1つが、歯の周りが丸く膨らんだり、全体的に赤く腫れたりすることです。
これは、歯肉や周囲の組織に細菌が侵入し、体が細菌と戦った結果として生じた老廃物(膿)が溜まり、それが炎症反応を引き起こします。膿がたまった箇所を指で押すと、ブヨブヨとした感触があったり、痛みを感じたりすることもあるでしょう。
嚙んだ時に痛む
歯の根の先端や歯の周りに膿がたまると、その膿の塊が組織を内側から強く圧迫します。この圧迫された状態の組織に対して、食事などで歯を噛み合わせたときに外部からの力が加わることで、痛みを引き起こすことがあります。
頭痛がする
歯茎にたまった膿が神経を刺激し、それが痛みとして頭に伝わる結果、頭痛が発生することがあります。
特に上顎の奥歯に問題がある場合、膿が上に広がりやすくなるため、頭痛として感じられることもあるでしょう。
歯茎に膿がたまる原因は?
歯茎に膿がたまる原因には、歯周病の進行や歯の内部の感染、外傷など、いくつかの理由があります。ここでは、代表的な原因を解説します。
歯周病
歯茎の膿がたまる一般的な原因の1つが歯周病です。歯磨き不足などにより、歯肉や歯根膜、そして歯を支える歯槽骨といった歯周組織に細菌が侵入し、慢性的な炎症を起こしてしまうことで、歯周ポケットが深くなります。
この深くなったポケット内で細菌が活発に増殖し、膿を形成してしまうのです。
根尖性歯周炎
歯の内部にある歯髄(しずい)と呼ばれる神経が、深い虫歯菌などに感染すると「歯髄炎」が生じます。この炎症がさらに悪化し、細菌が歯の根の先端(根尖)に達すると「根尖性歯周炎」が発生するでしょう。
歯根嚢胞
歯根嚢胞(しこんのうほう)は、前述の根尖性歯周炎が慢性化することによって起こります。これは歯の神経が死んだ後、歯の根っこの周辺に袋状のものができる病気です。これが歯茎から膿を出す原因となることがあります。
歯根破折
歯ぎしりや食いしばり、過去の治療による影響などで歯が折れたり割れたりする「歯根破折」が起きると、その隙間から細菌が内部に侵入し、感染症を引き起こすことで膿がたまる原因となることがあります。歯根破折は治療が難しく、抜歯が必要になるケースもあります。
親知らず
親知らずが中途半端に生えていたり、斜めに生えていたりする場合、周囲の歯茎が炎症を起こしやすくなります。
親知らずが磨きづらく、清掃しにくい場合も、細菌が繁殖して歯茎から膿が出ることがあります。
歯茎に膿がたまった時の応急処置
歯茎に膿がたまり、痛みや腫れが出た場合は、すぐに歯科医院を受診することが最善です。しかし、夜間や休日など、すぐに受診できない場合の応急処置を解説します。
患部を冷やす
患部が腫れや痛みをもっている場合は、冷やすと痛みが和らぐことがあります。水で濡らしたタオルやハンカチなどを、頬の上から患部に当てて冷やしましょう。
ただし、患部を氷で直接冷やすと逆に痛みが出る可能性があるので、注意が必要です。
痛み止めを飲む
日常生活に支障をきたすほどの強い痛みがある場合は、市販の痛み止め(解熱鎮痛剤)を服用しても問題ありません。薬剤が痛みを一時的に和らげてくれますが、これは根本的な治療ではありません。必ず歯科医院を受診しましょう。
口の中を清潔に保つ
口の中が清潔に保たれていないと、細菌が活発に活動し、歯茎からの膿や炎症がひどくなる恐れがあります。
食事後には優しく歯磨きをして汚れを落とし、うがい薬を使用して口の中を清潔に保ちましょう。ただし、膿が出ている部分を強く触ったり、無理に膿を出そうとしたりするのは、症状を悪化させる可能性があるため避けてください。
歯茎の膿はどのように治療する?
歯科医院では、膿の原因となっている病気の種類や進行度に応じて、適切な治療法が選択されます。
膿がたまる原因が根尖性歯周炎である場合、歯の根の中を掃除し、細菌を取り除く「根管治療(こんかんちりょう)」がまず行われます。
しかし、根管治療だけでは治らない場合や、根の先に大きな膿の袋(嚢胞)ができてしまった場合は、歯肉を切開し、膿の袋や根の先端を直接取り除く「歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)」といった外科的な処置が必要になることがあります。
また、歯周病が原因で膿が出ている場合は、歯周ポケット内の歯石やプラークを徹底的に除去する歯周病治療が行われます。さらに、歯根破折や重度に進行した歯周病などで歯の保存が不可能と判断された場合は、抜歯が選択されることもあります。
まとめ
歯茎や歯の根っこから膿が出ている状態を放置していると他の病気を併発する場合があり、悪化した場合、抜歯しなければならなくなる恐れもあります。
このリスクを避けるためには、歯周病や虫歯を日頃から予防し、歯茎の腫れや膿といった初期症状に気づいた場合は、早期に適切な治療を受けることが不可欠です。
応急処置で痛みが引いても、それは一時的なものであるため、歯科医院を受診しましょう。